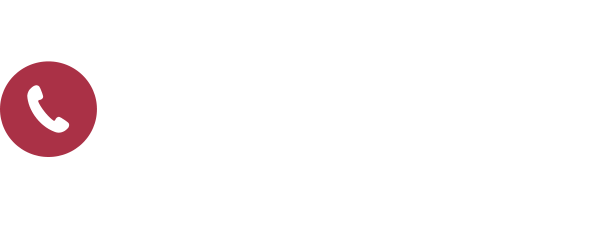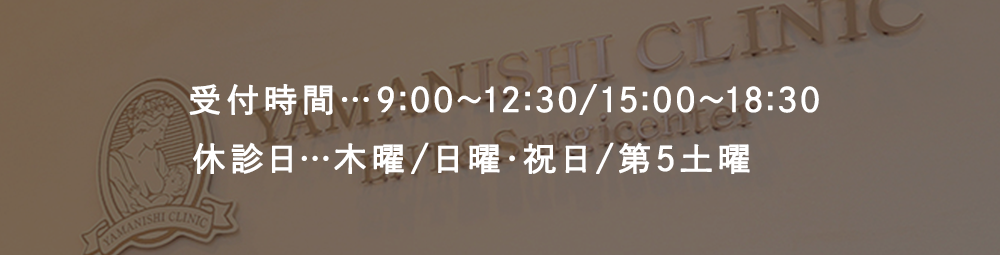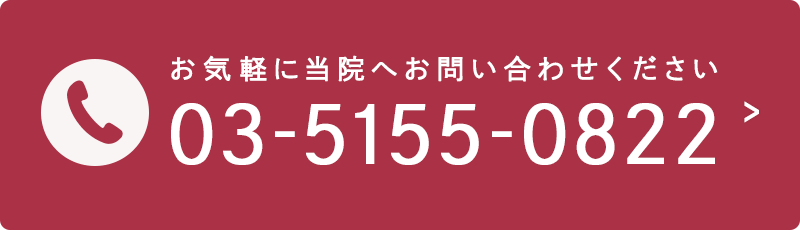高校時代の友人が26歳で亡くなってからもうすぐ30年が経ちます。
明るく気さくで誰とでも仲が良い楽しい男でした。
家に電話をすると必ず元気なお母さんがでてきて、階上にいる彼を大きな声で呼んでくれたのを昨日のことのように思い出します。
その後、彼はとある仕事に就き活躍しました。
数年して街で彼を見かけた時、あまりに雰囲気が変わってしまい、声をかけられなかったことが悔やまれます。
高校時代に彼が良く口ずさんでいた、彼自身が作った歌の詩を一部載せます。
街の風に引き裂かれ舞い上がった夢屑が
路上の隅で寒さに震え揉み消されてく
立ち並ぶビルの中ちっぽけなオイラさ
のしかかる虚像の中で心を奪われている
合掌